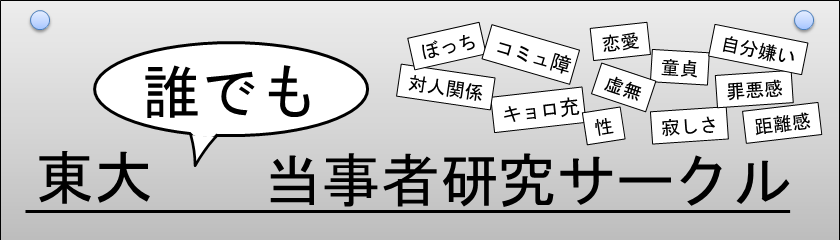実存の障害/生存の障害
執筆:べとりん
なぜ私たちは「生きづらい」のだろう。
単純に、「生存」に困難を抱えているのであれば、これは「障害」や「疾患」として扱った方が適切である。何らかの外的要因によって、命の危機に瀕しているというならば、病院が対処するだろうし、生きるのに必要な労働や食料が足りないというのならば、社会保障が対処すべき問題である。私たちが、特に私の周りの大学生が「生きづらさ」と呼んでいるものは、どうやらこの類ではない。
私は「生きる」ことを、大きく「生存」と「実存」に分けて考えたい。そして、「生存の障害」と「実存の障害」を分けて考えてみたい。「生きづらさ」という言葉が表しているものは、ほとんど「実存の障害」である。特に大学生の「生きづらさ」を分析する上では、私たちが考えるべきなのは実存と生存の対立である。「生きづらさ」を、この二つの「生きる」が対立して起こる体験として捉えてみる。
実存とは何か。
ハイデガーは、人間を「おのれの存在において、この存在そのものが問題であるような存在」であるとした。そして、このような存在の仕方を「実存」と呼んだ。「この存在そのものが問題である」とは、「『私という存在とはどのようなものであるのか』が問題になる」という意味である。私とは何か、私という存在は何なのか、その解釈が私にとって問題になるような在り方、それこそがハイデガーの言う「実存」である。
これは、サルトルの「主体」「客体」という概念を使うとわかりやすい。(「即自存在」「対自存在」という概念による説明もあるが、筆者がこの説明を好まないのでここでは避ける。)「主体」とは、「周囲の物事や自分自身をみずから解釈する在り方」。対して、「客体」とは「自分から他者や自分を解釈することはせず、他人から解釈されることで存在できるような在り方」である。基本的に物体は「客体」であり、人間は「主体」である。
たとえば、客体の例としてハサミを取り上げよう。ハサミは「紙を切る道具が必要だ」というハサミ製作者の目的が先にあって、その目的に合うようにその実物が作られる。ハサミには、作り手によって、生まれた時点ですでに「ハサミとは、紙を切るための道具である」というふうに解釈が与えられている。私たちは、ハサミを見ると、それが「紙を切る」という可能性と結びついて理解される。「ハサミは紙を切るもの」という図式の中で理解されるのであり、未来のある可能性の中で、すでに世界との関わり方を定められている。ハサミは、そのような存在の在り方をしているのである。
一方で、主体である人間は、何らかの目的をもって世界に生まれてくるわけではない。たとえ、親から「お前はうちの跡継ぎになるために生まれてきたのだ」と言われたところで、必ずしもそれに納得できるとは限らない。なぜならば、人間は自分で自分を自己解釈する存在だからである。「私は本当に跡継ぎになるためだけに生まれてきたのだろうか」「もしかしたらもっと別の目的があるのではないだろうか」と人間は悩む。サルトルは「人間は自由の刑に処せられている」と表現するが、将来私がフリーターになるのか、会社員になるのか、看護師になるのか、予め定められているわけではない。私は私を見ても、「それが世界とどのように関わる存在になのか」という理解を確定させることができない。私には「私は世界とどのようにかかわるかという図式」は与えられていないのだ。
このように、人間は、その存在目的を定められないまま、「物心がついた時にはすでに」世界の中に存在している。「客体」と違い、主体である人間は自分で自身を自己解釈するがゆえに、その存在理由が定まらない。
サルトルが「人間は自由の刑に処せられている」と表現したこと、このような存在の在り方そのものをハイデガーは「実存」と呼んだ。しかし、私が「実存」と呼んでいるものは、いわばこの「自由の刑」が解決されている状態のことを指している。より慣用句的な意味での「実存」である。
私の言う「実存」とは、「何らかの図式の中で何らかの向きに方向づけられており、今自分はその方向に進んでいると実感できているような存在状態」のことを指す。もしハサミに意志があるならば、「紙を切っている」とき、ハサミは実存を感じているに違いない。ハサミは解釈によって「ハサミは紙をきるもの」という図式を与えられ、それにより「紙を切る」向きに方向づけられているからだ。人は生まれた時には将来何になるかという解釈は与えられていないわけだが、「私とはこういう存在である」というアイデンティティを獲得し、その通りに生きられている時、人は実存を感じるといえるだろう。
わかりやすく言えば、実存とは、「自分の存在に意味を感じてられている状態」のことである。人は、自分のことを、「日本一のサッカー選手になる人間」だと思えば、サッカーの練習を通して実存を感じるかもしれない。「誰にも迷惑をかけない存在になる」と思っている人は、引きこもるということに実存を感じるかもしれない。人は、自ら解釈するところのものであろうとする。自分が考える「自分」の姿を実現しようとする運動、それが実存だと言ってよいだろう。人は、自ら解釈するところの「自分」に向かって、常に方向づけられているのである。
このような「実存」と「自己実現」は似た概念であることを申し添えておく。
自己実現とは、その人が自身の可能性を最大限発揮することを指す。ここでいう可能性とは、例えばハサミにとっての「紙を切る」や、鳥にとっての「空を飛ぶ」というものである。
繰り返すように、私たちはあるものを見ると、「それが未来のある可能性の中で、どのように世界との関わるかという図式」を通して理解する。私たちはハサミを見れば、「紙を切る」という可能性を思い描く。羽を見れば、「空を飛ぶ」という可能性を思い描く。
そして、それは自分自身についても同様である。自分、および自分の中に既在する様々な要素それぞれについて、「それが未来のある可能性の中で、どのように世界との関わるかという図式」を通して理解しようとする。ある人は、「自分が女性である」ということから、「将来子供を産み育てる」という可能性を思い描くかもしれない。ある人は、「昔から絵を描くのが好きだった」ということから、「絵描きになる」という可能性を思い描くかもしれない。そして、このような可能性に向かって行動し、それを実現しようとすることを「自己実現」と呼ぶ。
「自己実現」は、「実存」の一種だと捉えることができよう。
「実存」と「生存」を対立させることで、理解しがたいいくつかの現象は整理しやすくなる。事実、「リカバリー」概念などを巡る精神保健分野の障害学の歴史は、まさに実存と生存の対立だったと言ってよい。
チューブにつながれてベッドに寝ているだけでも、生存自体は可能である。精神科であれば、まさに数十年前は、「薬漬け」と呼ばれる状態が横行していた。現代でも、自殺や自傷の恐れがある患者に対しては、議論はあるものの、身体拘束の使用がおこなれている。
こういった行為が問題になったのは、「患者はモノではない」からだ。患者を一人の人間として扱うようなケアへの転換が行われてきたが、これはまさに患者がどのように解釈されるかを巡る争いである。
私たちはモノではないがゆえに、私がどのような存在になるかということに悩まざるを得ない。「承認欲求」の問題、「コミュニケーション」の問題、大学生が抱える多くの問題は私たちがモノではないがゆえに起こる。「モノ」とは、つまり「客体」、「自分から他者や自分を解釈することはせず、他人から解釈されることで存在できるような在り方」のことだ。現代の日本は、情報も、資源も、いざというときのセーフティネットも、かなり揃ってきている。「もし完全に社会や制度が期待するとおりに生きることができるならば」生きていくだけには困らないだけの制度は整っているハズではないか。それでも生きづらいのは、社会の期待するとおりに生きることが困難でつらいからであろう。そのつらさを言語化するには、「私」を巡る解釈の争いに目を向けなければならない。
一方で、もし本当に「モノ」に成りきってしまおうとすれば、それはそれで楽であろう。「モノ」、すなわち「客体」になってしまえば、私という存在の解釈は他者によって決定される。その他人からの解釈に従うだけでよい。私の解釈され方は一意に定まる。このような在り方の代表的な例が「依存」や「嗜癖」である。たとえば、相手からの期待に応え続けようとするだけの存在になることは依存の一種である。相手の期待のままに動くだけの「お人形」になるのである。これは、何らかの解釈を与えられ、その解釈によって方向づけられる向きに進んでいるという点で、間違いなく「実存」である。
だが、このような生き方は生存には向いていない。「お人形」は守ってくれる人がいなければ生きていけない。自分の利益は自分で守るということが必要である。様々な他者から自分に投影される解釈の中で、自分に有利に働くものだけを選択し、それ以外を突っぱね、自分で自分を解釈していかなければ、生存は難しい。
別の視点から、実存と生存の対立について述べてみる。
実存において、命とは「別の目的のために消費されるべきもの」であり、生存において、命とは「目的そのもの」である。
「武士道とは死ぬこととと見つけたり」という言葉があるが、端的に実存と生存の対立を表している。
この言葉に従えば、武士道とは、忠義のためならば、いつでも自らの命を捨てる覚悟のことであろう。
このような覚悟、武士道を持って生きるならば、その人は常に自分の目指す目的に向かって人生を生きることができるに違いない。
その人はまさに「武士」として己の在り方を定義している。
仕える先の人から「武士」として使われること。
場合によっては、武士として「使い捨てられること」にこそ、意味(武士道)を見出している。
これはまさに「実存」である。
だが一方で、これは明らかに「生存」には反している。
「これのためになら命を捨ててもよい」というような「価値」を持つことは、
生存には不利にはたらく。
生存において、命よりも高次の目的は存在しえない。
もし命よりも高次の目的を持とうとするならば、それは「生存の障害」と呼ぶべきものである。
例えば、それが「償い」という価値を目指したものであっても、「自殺企図」は「障害」として扱われるだろう。
例として、「紙を切れなくなったハサミ」について考えてみよう。
ハサミは紙を切るために作られ、生まれてきたが、いずれは刃こぼれし、紙を切れなくなる。
このようなハサミが、もし「生き残っていく」としたら、どうすればいいだろうか。
一つの答えとして、「別の使われ方をする」という方法があるだろう。
釘を打つ、定規代わりに使う、など。
あまり用途は少なく、そのために作られたものに比べれば数段劣るが、それによって生き延びていくことが可能かもしれない。
生存とは、まさにこのような在り方である。
生き残るためなら、「紙を切るためのもの」という「自分の定義」「自分に与えられていた解釈」「自分の目的」を捨て、
別の定義に書き換えられることも辞さない。
「実存」とは、「自分とはこういう存在である」という自分の定義を手に入れ、それに従って生きることであったが、
「生存」は、自分の定義を常に書き換えていかなければならない。
哲学の思考実験で、「人間の身体を少しずつ入れ替えていったら、どこまで自分の身体と言えるのか」というものがある。
髪をカツラに変える。腕を義手に変える。足を義足に変える。肝臓を移植される。心臓を取り換える。脳を取り換える。
だが、何もしなくても私たちの細胞は、常に置き換わっている。
私たちの生存とは、常にこのような在り方だといえよう。
「生き残る」ためなら、今までの自分を構成していた解釈を常に取り換えることが必要である。
例えそれまでサッカー選手になりたいと思い、自分のことを「サッカー選手になる」という未来と共に理解してきたのだとしても、
生きるためならばサラリーマンになるしかないかもしれない。
私たちは生きるために、常に自分の「実存」の一部を取り換えているようなものである。
「概念堕ち」の項で述べているように、
ある他者によって、一つの解釈に定められるような存在(概念)、固定的で不変の存在になりたいと願う時もある。
だが、人間であるからには、一つの解釈に決定されるものではなく、相反する様々な解釈にさらされ、そのゆらぎの中で自分を定義していく必要がある。
「実存の障害」/「生存の障害」という分け方を使うことで、
実存のために固定の一つの解釈にしがみつこうとする私と、一方で生存のために別の多様な解釈を受け入れざるを得ない私の、
二極に引っ張られる私の揺らぎを捉えることができる。
*おまけ1
「社会に適応する」とは、生存することと実存することが一致するような「解釈」を得られるようになること、と定式化することもできよう。
例えば、「父親」という役割「自分は自分の子供を大人になるまで育てるために頑張る」という自己解釈は、子供が大きくなるまで自分が生存することを必要とする。実存のために生存が必要であるならば、それは「実存」と「生存」の対立が弱まることになる。
現代社会においては、生存するためには、多くの場合お金を稼ぐことが必要である。「社会の一員」として、「社会に貢献する」という自己解釈は、労働しお金を稼ぐこととを通じて実存を可能にし、「実存」と「生存」の対立を弱める。
また、「社会的に容認されるお金のかからない趣味を持つこと」も、「生存」と対立することなく、「実存」を達成できる点で、「生存」と「実存」の対立に貢献するかもしれない。