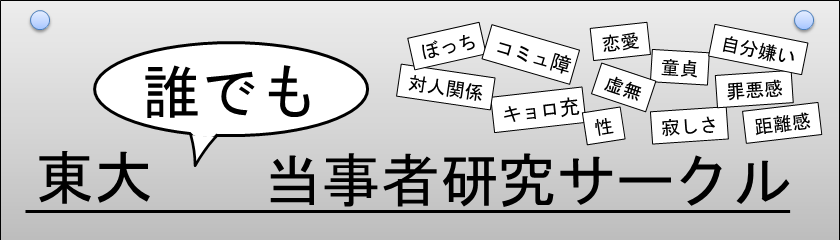「生きづらさ」とは何か
執筆:べとりん
・「障害」から「生きづらさ」という表現への変化
近年、「生きづらさ」という概念が注目されつつある。京都大学で「生きづらさ学」の旗揚げ宣言がなされたり、NHKでもタイトルに「生きづらさ」を冠する番組が放送されたり、東大では「事例でみる生きづらさ」という名前の講義が行われたり、「生きづらさ」を含むタイトルの学術書がいくつも出版されたり、「日本生きづらさ大全」という書籍の出版のためにクラウドファンディングで100万円が集まったりと、「生きづらさ」という言葉は少しずつ広がっているように思う。
なぜこのような表現が流行るかといえば、「生きづらさ」としか表現できないような問題、周囲からでは観測の難しい形で生きることを阻んでいるものに注目が集まっているからであろう。健康科学の領域にいても、「perceived
stigma」とか、「曖昧な喪失」とか、今までの障害の概念ではとらえられないような概念を論文に触れることがある。
「生きづらさ」に一番近い既存の表現はおそらく「障害」である。WHOはICF(国際生活機能分類)の中で「障害」の定義を定めている。その中で、「障害」は大まかに「機能・形態障害」(例:指が動かない)「活動障害」(例:文字が書けない)「社会的参加の制約」(例:手紙が出せない)に分けられる。どれも基本的には、「何らかの行為や活動、実践を阻むようなもの」のことを障害と定義する、という点では一致している。障害という言葉の字句通り、何かの目的達成を阻む物を「障害」と呼んでいる。
ここに「障害」という表現の限界がある。その人の意図や意志を妨害するから「障害」なのであるから、その「障害」は、その人の意志でコントロールできる範囲の外側になければならない。その「障害」が、その人の意志ではどうにもならないと社会的に認められなければ、「障害」とは呼べない。悲しみ、絶望、やる気が出ない感覚、プライド、自意識、といった、その人の主観に属するものは、「障害」という概念では扱いづらかった。
一方で、「生きづらさ」という表現は、「障害」よりも本人の主観的な感覚や体験に重きを置いている。「生きづらさ」とは、その人の感情や気持ち、その人の体験そのものを指している。それゆえに、周囲からは欠陥が観測できなくても、その人が困難を感じていれば、それは「生きづらさ」という言葉で扱うことができる。当事者活動も、このような客観的にはとらえがたい「生きづらさ」のようなものを扱うための試みの一つということもできるかもしれない。
現在、「現象学」や「社会構築主義」などの立場から、「生きづらさ」を分析する書籍や研究が多数出てきている。たとえば、大塚類 遠藤野ゆり 編著『エピソード教育臨床 生きづらさを描く質的研究』では、現象学的な視点を用いながら、自閉症スペクトラム障害を持つ人の実際の経験や、甘やかされて育てられることの生きづらさについて、本人の体験そのものに忠実に、かつ学問的に記述している。草柳千早著『「曖昧な生きづらさ」と社会―クレイム申し立ての社会学』では、夫婦別姓を巡る様々な立場の意見やセクシャリティに関するアンケートなどを事例として取り上げながら、ある人の「生きづらさ」というものが社会的に問題として認められるために必要な過程、「現実を巡る解釈の争い」について詳細に記述している。
「障害」から「生きづらさ」という表現への変化は「本人の生きている世界」の中を探索しようとする試みが隠れているように思う。当会でも、このような在り方の「知」を形づくることができればよいと思っている。